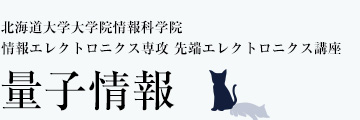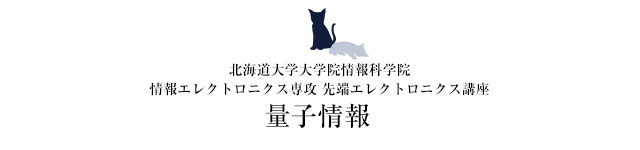量子情報:北海道大学大学院情報科学研究科情報エレクトロニクス専攻先端エレクトロニクス講座
研究テーマ
超伝導量子コンピュータ

有用な量子コンピュータの実現に向けて現在最も実装が進んでいる物理系です。通常の光とは周波数領域が大きく異なりマイクロ波領域となりますが、量子光学を用いて制御、操作をするという意味では物理の原理は共通するものがあります。今後の大規模化に向けた分散処理を目指して、マルチチップ間での共振器接続やマイクロ波通信接続などを行います。また中小規模の量子ビットで行える量子アルゴリズムの実装、量子誤り訂正、量子誤り抑制の実装なども行えます。
光量子コンピュータ、量子通信

光を用いた量子計算、量子通信などの量子情報処理の実装実験が行えます。光の大規模化、集積化に向けて重要な要素技術の実装や中小規模の量子計算、量子通信の実装実験が行えます。また光は原子系の量子コンピュータを接続し分散処理を行うための重要なインターフェースとなりますので、それに向けた研究も考えていきたいと思います。
光子と原子の量子インターフェース

図:Phys. Rev. A 111, L011701 より
単一光子の生成効率を上げたり、光子・原子間の量子ゲートの精度を上げるために、共振器量子電磁力学(Cavity QED)を用いた実装方式を検討します。これまで主に理論で検討を行ってきていますが、このような実験を行っている研究室との交流も可能です。
冷却原子による量子コンピュータ

図:Physical Review Letters 112, 110501より
冷却原子を光ピンセットを用いて規則的に配列し、別途量子ゲート操作を行うことで量子計算を行う冷却原子アレー方式と光格子中に冷却原子をトラップする方式の2通りあります。大規模化に向けて最近注目されている方式です。光エレクトロニクス研究室でこれまで使われてきた空間光変調器(SLM)などの技術が今後役立つ可能性があります。
誤り耐性量子計算のアーキテクチャや効率化の研究

図:符号化した論理量子ビットの演算の様子(HPCA2025より)
量子計算はノイズの影響が避けられないため、量子誤り訂正符号を用いて誤り耐性量子計算を行うことが大規模化に向けて必須と考えられています。符号化したまた量子演算を行っていくためにどのような符号を用い、どのように演算を行い、どのように複合するか、物理系にも応じて最適化の方法が異なってきます。幅広いレイヤを考慮しながらこのような最適化をどのように行うか良いアーキテクチャを検討します。
量子誤り抑制や量子・古典ハイブリッドアルゴリズムの研究

図:PRX Quantum 3, 010345 より
量子コンピュータの規模はまだそれほど大きくないため、量子ビットのリソースを抑えたままなるべく有効な計算ができるよう、古典計算も合わせて活用したハイブリッドな量子計算の手法を考えます。

北海道札幌市北区北14条西9丁目
北海道大学情報科学棟502号室
tel./fax 011-706-6521